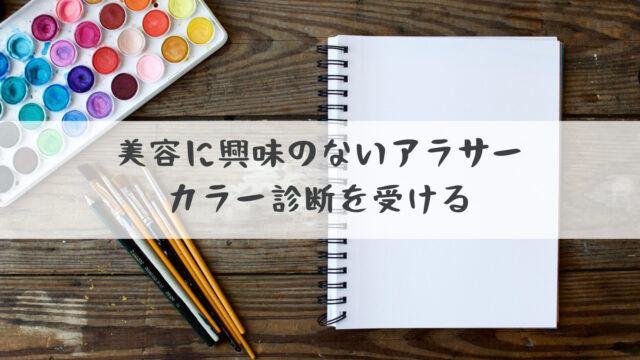海が好きだ。
そう言うと、なんだか微妙な反応をされることがある。
どうやら一般的に海というものは、パリピが集い、若さに任せて男が女に声を掛け、一夜の過ちを犯す場所と考えられているらしい。
少し前まで、そういう反応をされるのが嫌で、海が好きだと周囲に言わないようにしていた。
でも最近、隠すのも馬鹿馬鹿しくなって、打ち明けてみることにした。
いつものように微妙な反応をされた後、
「海に行っても、何もしないんです。浮き輪で、ただ浮いてるだけです」
と続ける。
そうすると、相手は大抵笑う。理解できない、という笑いだ。
そこでいつも、話はおしまい。
私の話はそこからが重要なのだけど、
大抵の人は、その続きに興味を持たない。
私にとって海は、自分が社会性のある生き物だということを、忘れさせてくれる場所だ。
物言わぬ空と、私を抱えてくれる温かな海水、遠くに見える荒々しい山々と、そこに生えている木々の緑が、ただあるだけ。
それ以上でもそれ以下でもない。それが、私にとっての海だ。
パリピと陰キャ、若者と年長者、清楚とビッチ、美人とブス、痩せとデブ。そういう区別が、海にはない。
だから、海にいると、ほっとする。海は、私を何者にもしない。私に何も求めない。
海にいる間は「ただの私」でいられる。それが心地よい。
海に入ると、最初は海水が冷たく感じられる。
でもすぐに、体温が馴染んでいく。
しばらく浸かっていると、海水と皮膚の境目がなくなって、身体がゆるゆると溶け出していきそうな心地になる。
浮き輪と共に、沖へ泳いでいく。
波打ち際から遠のくほど、波は穏やか。
ゆりかごに寝そべるような気持ちで、浮き輪に座り、波に揺られる。
そのとき私は、偶然枯葉に乗って流された虫みたいに、ちっぽけな生き物になる。
そして、ゆっくりと景色を眺める。
砂浜とか、その後ろの山々とか、宇宙を感じるほど深い青色をした空とかを、しっかりと目に焼き付ける。
現実世界の雑音の中に戻っても、この景色を思い出せるように。
私がどんな役割を演じているときでも、「ただの私」が、私の中にいるのだと、思い出すために。